








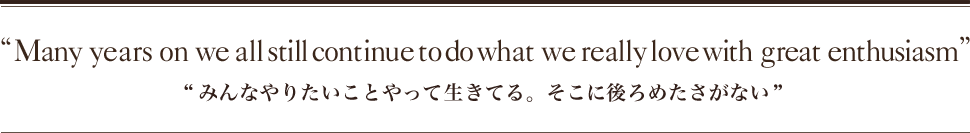
思った以上にタフでさ……。言葉は分からないし部屋も決まらない。お金もすぐに底を尽きて、空はどんより曇っているし食事も不味い。その頃のことは忘れられないな。」
渡英当初は部屋すら決まらず、薄暗い物置きのようなスペースで寝泊まりして凌いでいた。ようやく決まった部屋も、ベッド一つ置くと他にくつろぐスペースすらない小さな空間。思い描いていたクリエイティブな仕事などなく、結局日本と同じ工事現場の仕事で毎日クタクタ。会話の一つも成り立たなく、思った以上の過酷な環境に気持ちが沈む毎日を送っていた。
そんな中での唯一の楽しみは、休日に電車で足繁く通ったマーケットだった。古着を見たり触ったり、それだけが楽しみになっていった。
数年が経過し英語にも少しずつ慣れ、徐々に自分と同じような感性を持った仲間もでき、ゆっくりとだがその輪は広がって行く。継続してやり続けていた古着のバイイングも、その頃には小遣い稼ぎくらいになっていった。
「ロンドンで何を学んだって、フォーカスすることじゃないかな。」
勝手の良い日本と違い、異国の土地での生活は出来ないことだらけ。しかしある意味何に対してもフリーダムな国なので、自分次第で状況はガラッと変えられる。本当に自分が楽しめるもの、好きなものって何だろう?と問われる毎日を過ごす中、徐々に視界が開け、感覚が研ぎ澄まされていく。
やっぱりオレは古いアメリカのファッションやプロダクトやカルチャーが好き。それをもっと突き詰めていきたい……。
なんとなくで突っ走ってきた東京時代と違い、自分のアイデンティティが徐々に形成されていくのを実感したという。何かあるかもしれない、何かやれるかも……という淡い期待は無駄でしかない。結局、自分が通って来た道にしか自分の道を切り開くすべはない、ということを身を以て体感した。自分の方向性が定まって行く中で、気持ちもポジティブになり行動範囲も広がって行く。
彼のタトゥーはこの頃に本格的に彫り出したという。世界的に有名なチェッカー デーモンタトゥのルーク・アトキンソンに彫ってもらいにドイツまで旅もした。
Although he didn't know it at the time, he was in for the surprise of his life.
“London, looking back was one of the hardest, but, one of the most rewarding experiences of my life. At first it was nothing like I imagined it to be. It made the life I had left behind in Tokyo look very comfortable in comparison. It was a lonely time and I would often think about the friends I had left behind. London was cold, dark, the food was bad and I could not speak English. My girlfriend and I were living in a shared house, a room in the basement, with no windows and only just bigger than the bed itself. It was all we could afford”.
“It was tough for the first few years, in particular the language barrier. The only thing that made me forget everything was going to the flea markets and looking at all the vintage clothing I loved”.
But once again his determination and the freedom to create his future, kept him going. “I did not have this kind of motivation in Tokyo, something was different for whatever reason. All I knew was that under no circumstances would I return to the same situation in Tokyo. So I am very grateful for this experience, it taught me so many things, most importantly I found my focus”.
After a few years, still with limited English capabilities, he started to make friends with similar interests and through them he also started to become more interested in Tattoos. One his earlier tattoos was during a trip to Germany, by Luke Atkinson from Checker Demon Tattoos.

「たとえそれ(服)がくたびれようが、それを着続ける。そんなタフな存在でありたい。」
2010年、邊見は30‘S~50’Sの中でも素朴なルーツワークやクラフト感、インダストリアルが融合するようなプロダクトにインスパイアされた物作りにフォーカスして行く。
「こだわっているのはやっぱりパターン。細かいディテール云々と言うよりは、ビシッと男らしいシルエットで魅せる。テキスタイルにもこだわり、耐久性のある服じゃないと面白さを感じない。」
TIMEWORN CLOTHINGの洋服は確かに一見ベーシックながら、着た際にピンと背筋が伸びるような感覚になる。一見地味にも見えるがスーツを着ているような感覚? とでも言えようか。そんなところからもパターンにこだわって丁寧に作られていることを実感できる。ワークもミリタリーも万人向けのユニフォームとして派生したルーツを思い返すと、着用する人間のキャラクター次第で如何ようにも見栄えは変わる。TIMEWORN CLOTHINGの洋服もそんなユニフォームに通ずるように、分かりやすいロゴが入ることもなく、着用する人間のパーソナリティが投影する洋服と言える。メディア露出も少なく、認知度がある訳でもない。それでも興味を持って来てくれるお客さんと向き合い、ゆっくりと、だが確実に自分たちの世界観を広げている。
「こんな感じでやっていると、お客さんも芯を持って来てくれる。だからこそ強く長い信頼関係を築けるのだと思う。店の空気を感じながら、手にとってプロダクトを見てもらう。」
移り変わりの早いシーンとは無縁なお客さんに応えるように、お店ではゆっくりと時間をかけながらコミュニケーションを取っている。
彼らのライフスタイルの一部であるバイクもTIMEWORN CLOTHINGクルーは独特のカラーが滲み出ている。純正スタイルと言われる目立つカスタムを施さないものや、1930〜40年代に流行したダートトラックレースに講じる人々が行っていたボバースタイルに傾倒している。見た目の派手さはないが、彼らの作るクラシカルなウエアにはマッチする。特に意識していないという邊見だが、知らず知らずのうちに彼ら独自の足跡を世の中に残しているのかもしれない。
「もう10代からの付き合いだから、不思議な感覚。ガキの頃と変わらず、みんなやりたいことやって生きてる。そこに後ろめたさがないから、たまに会ってもすんなりと会話が弾む。」
歳を重ねるにつれ互いに一緒に過ごす時間は少なくなるのは自然な流れ。しかもお互いにまったく違う生き方をしていると、話が弾まなくなるようなことも多いだろう。もちろん彼らは同じ業界にいるので共通の話題には事欠かないだろう。だがそんな表面的なことではなく、やりたいことをやって生きている互いを理解し、それに敬意を払っているからこそ良き関係が築けていると邊見は言う。前章の眞野の話にもあったように、そうやって生きることが想像以上にタフであることを各々が理解している。そしてそのベースには、良きも悪きも包み隠さずさらけ出すというストレートな人間関係も見え隠れする。実際に彼らの話は歯に衣着せぬ物言いで潔い。そのように根っこから深く繋がっていて自分たちのやっていることに偽りがないからこそ、一種独特の空気感を出せたり違うフィールドで活躍していても同じような雰囲気を醸し出せるのだろう。彼らの本質や共通する『何か』は、このあたりに大きなヒントがある。
取材後、邊見が本棚から徐に取り出したのは、古いウールの生地スワッチ。ルーペで見ながら縦何本、横何本と数えて、旧き時代へ思いを馳せる。それを語っている邊見の姿は一点の曇りもない笑みで溢れていた。
そんな何気ない1コマにも彼らがタフに生きている所以が詰まっている様に感じた。
第三章では更に西浦の視点を加え、彼らの考え方や関係性の先にあるクリエイティブについて迫っていきたい。
第三章へ続く
Fast forward to 2010, when Kei Hemmi created “TIMEWORN CLOTHING” a project very close to his heart. He began to focus wholeheartedly on the quality of his garments, the patterns, fabrics and silhouettes and after many years of experience, came to realize that the most important thing for him was to have clothing that he wanted to wear for many years to come and no matter how worn the fabric or old the style that feeling or connection with a particular piece remains special. This is the feeling he wishes to pass on to his customers.
Time moves forward and inevitable changes occur but Hemmi, Nishi and Mano still remain friends. “We have been friends since our teens and with each passing year we see less of each other. Nevertheless, our respect for one another is undeniable and so when the opportunity arises to meet up we always have a good laugh”.
“One of the many things that I am very grateful for is that even nowadays many years on we all still continue to do what we really love with great enthusiasm”.
Towards the end of this of this frank conversation with Hemmi, he is in a very nostalgic mood. Picking up a vintage fabric swatch from his bookshelf he starts to smile and talk keenly about the integrity of the fabric, the weave, fibres, drape and so on. We feel privileged to have had a chance to hear about some of Hemmi’s personal experiences and a small glimpse into his world and undeniable devotion to his craft.
Continue to Episode #3.

Kei Hemmi邊見 馨
東京生まれ。AT LAST、TIMEWORN CLOTHING、BUTCHER PRODUCTSの3ラインで構成されるTIMEWORN CLOTHINGのディレクター。
Kei Hemmi Born in Tokyo, Japan - Creator and Director of TIMEWORN CLOTHING, AT LAST and BUTCHER PRODUCTS.